「なぜかこの家では、片づけるのが苦じゃない」
「自然と動きたくなる家ってあるよね」
こうした感覚は、決して偶然ではありません。 人の行動は、空間やモノの配置、光や音といった“環境”によって、無意識に影響を受けています。
今回の記事では、認知科学の視点から、“動きたくなる家”と“片づけたくなる家”の違いを解き明かします。 単なる家事ラクや収納テクニックではなく、人と空間の関係性に注目した新しい家づくりの考え方をお伝えします。
なぜ人は“動きたくなる”のか?―行動は環境に支配されている
毎日を過ごす住まいの中で私たちはどのように動いているのでしょうか。朝起きて顔を洗い、キッチンへ向かい、必要なモノを取り出して身支度を整える。その一連の動きの中に「考えて動いている」ことは意外と少ないものです。
人は目に入る情報や身体の動きやすさ、光や音、気配といった“環境”の要素に無意識に反応し、それに沿った行動をとる傾向があります。これは脳がなるべくエネルギーを使わずに行動を選択しようとする仕組みによるものです。
つまり、空間の設計や配置によって、私たちの“日々の動き”そのものが変わる可能性があるのです。では、どのような環境が「自然と動きたくなる」家を生むのでしょうか?以下で詳しく見ていきましょう。
意識より“無意識”で動いている
人間の行動の多くは「つい」「なんとなく」で起こっています。これは、脳がなるべくエネルギーを使わずに効率よく判断・行動しようとする性質によるものです。そのため、脳はわざわざ思考を介さずに済む“無意識のルート”を優先する傾向があります。
このとき大きな影響を及ぼすのが「空間のつくり」です。視線の抜け、動線の分かりやすさ、明るさの変化といった空間の条件が、自然な行動を導く“ガイド”のような役割を果たしているのです。
つまり、意志の力ではなく環境によって、人の行動は驚くほど左右されているのです。

誘導される動線、止められる動線
たとえば、行き止まりの廊下や物が散乱したスペースでは、心理的な抵抗感が生まれ、無意識のうちに立ち止まったり、引き返したくなったりします。これは、行き先が見えないことによる不安や視覚的な混乱によるストレスが影響しています。
一方で、回遊動線のように入口と出口がつながり、視線が自然に抜ける設計では人はストレスなくスムーズに移動できます。
動きが遮られないことで「この先に行こう」という意欲が無意識に喚起されるのです。
つまり、動線の設計ひとつで、行動の“起点”が大きく変わる可能性があるのです。

“片づけたくなる家”には理由がある。環境が行動を後押しする
どれだけ収納スペースを用意しても、なぜか片づけが続かない。 逆に、収納量がそこまで多くなくても自然と片づけたくなる家が存在する。 その違いは、実は「モノの多さ」や「性格」ではなく、“環境”にあるのです。
認知科学の視点では人の行動は意志や習慣以上に空間からの“無意識のサイン”に影響されているとされています。 視界の情報、手の動きやすさ、決断のしやすさなど、片づけにまつわる行動にも環境の工夫が深く関わっています。
ここでは片づけを「頑張ること」ではなく、「自然にやりたくなること」に変えるためのヒントを考えていきます。
戻したくなる収納には「視線と手の動き」の秘密がある
人は、視界に入ったモノに手を伸ばしやすく、さらに「手を動かすまでの心理的距離」が短いと、自然と片づけようという気持ちになります。たとえば、扉を開けなくても使えるオープン収納や、日常的に使うモノをワンアクションで戻せる配置などがこれにあたります。
また、視線の整理も重要です。ごちゃごちゃとモノが視界に入る状態は「どこに戻せばいいか」が曖昧になり、片づけの意欲を削ぐ原因になります。反対に、視覚的なノイズが少なく、戻す場所が一目でわかる家では、迷いなく手が動き、片づけの行動が“自然な習慣”として定着しやすくなるのです。

片づけやすい家は「決断」がいらない
モノの“住所”が明確に決まっていると、「ここに戻そうかどうしようか」といった小さな迷いが生まれません。人は何かを片づける際、「どこに戻すべきか」を判断するために、わずかでも脳のエネルギーを使います。この“判断の手間”が蓄積すると、徐々に片づけが面倒になり、後回しにされていくのです。
一方で、あらかじめ戻す場所がはっきりと決まっていて、それが日常的な動作の延長線上にある場合、片づけは「考えることのいらない動作」になります。こうした“意思決定の省略”によって、片づけという行動は苦労の対象ではなく、暮らしの一部として自然に定着していくのです。

空間が人を動かす!暮らしを変える“5つの環境要素”
「この部屋に入ると自然と歩きたくなる」
「あの場所に行くと、なぜか落ち着いて片づけを始めてしまう」
そんな経験はありませんか?
私たちが日常的にとっている行動の多くは、実は“環境”によって導かれています。視覚・聴覚・触覚・嗅覚といった五感に働きかける空間設計が、無意識のうちに人を動かし、暮らしの質を左右しているのです。
ここでは、住まいにおける「動きやすさ」「片づけやすさ」「居心地の良さ」を形づくる、5つの重要な環境要素に注目してみましょう。
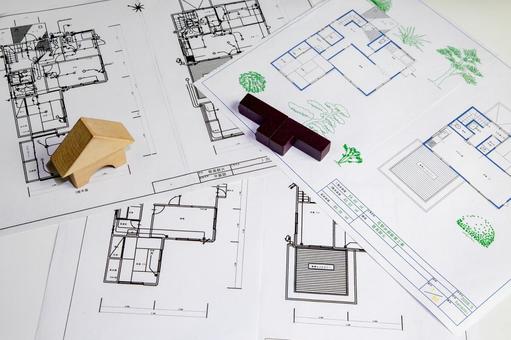
① 動線:動くことを自然に促すレイアウト
洗面所とファミリークローゼットを隣接させる、キッチンと玄関からのアクセスを短くするなど、無駄な動作を減らすことで、“自然と動く暮らし”が叶います。
② 視線:視覚的に“やる気”を引き出す配置
目線の先に目的地が見えると、人は自然とそちらに動きます。逆に、死角が多すぎると無意識にストレスがかかり、行動が鈍くなります。
③ 明るさ:日常動作のトリガー
朝日の入るリビング、明るい玄関などは、行動のスイッチになります。暗い空間は、行動を抑制する傾向があるため、照明計画は慎重に設計すべきです。
④ 音:音環境が“気配”と“集中”をつくる
静けさが必要な書斎には吸音設計を、家族の気配を感じたいLDKには開放感のある音環境を。音も暮らしを左右する重要な要素です。
⑤ 匂い:行動の記憶とリンクする“嗅覚の力”
玄関のアロマやキッチンの匂いなど、匂いは「記憶」と「気分」を結びつける役割があります。香りが心地よい空間は、人を引き寄せる力を持っています。
家事ラク・収納テクニックとは異なる「設計で変わる暮らし方」
「収納が多い=片づけやすい」ではありません。 「家事動線が短い=暮らしやすい」とも限りません。
たとえば収納の数を増やしても、それが日常の動線から外れていたり、使う場所と離れていたりすると、逆に“片づけにくい家”になってしまうこともあります。同じように、家事動線が短くても、動く方向にストレスがかかったり、回遊性がなく行き止まりが多ければ、かえって使い勝手が悪くなる場合もあります。
本当に暮らしを快適にするのは、“行動を自然に促す設計”です。つまり、動きたくなる、片づけたくなる、休みたくなる。そうした無意識の行動をサポートする空間こそが、暮らしの質を高めるのです。
住む人の無意識に寄り添い、判断の負担を減らし、心地よい動きを後押しする住まい。それが、ストレスの少ない快適な家づくりの核心なのです。

まとめ:暮らしを変えたいなら、“人間の認知”から間取りを見直す
家を整えることは、心を整えること。 “動きたくなる家”“片づけたくなる家”は、住む人の認知と無意識に働きかける設計によって生まれます。 機能性やデザインだけでは見えにくい、“暮らしのしやすさの本質”を、ぜひ設計段階から考えてみてください。

レンガの家専門 SEISYO三重支店
SEISYO三重支店ではレンガの家、クラシック住宅を中心に家づくりをしています。新築をご計画の際には、ぜひご相談ください。
お問い合わせはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://seisyo-co.jp/contact/
LINE公式アカウント
SEISYOの公式LINEアカウントでは、家づくりに役立つ知識やイベント情報をいち早くお伝えしております。これから家づくりをお考えの方は、ぜひご登録ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://lin.ee/ehujE0m
著者プロフィール
中島 盛夫
株式会社盛匠代表取締役[保有資格:二級建築士、宅地建物取引士]
大工としてひたむきに走り続けていた26歳のある日、お客様の娘様から頂いた現場での一言、 「良い家を作ってくれてありがとう」その言葉に建築への想いが膨らんでいく気持ちに気づいた私は、 「家づくりの最初から最後まで、じっくりをお客様と対話して、一生のお付き合いがしたい」と感じ、SEISYOを立ち上げました。