家づくりを検討する際、「できるだけコンパクトに抑えたい」「でも、狭く感じるのはイヤ」という声をよく耳にします。特に30坪以下の家では、限られた面積をいかに効率よく使い、“広がり”を感じられる空間にするかが重要なポイントです。今回は、そんな限られた空間の中でもゆとりある暮らしを実現するための「間取りの工夫」をご紹介します。
回遊動線でムダをなくす
限られた面積で生活をスムーズにするためには、「回遊動線」の考え方が非常に重要です。回遊動線とは、廊下や出入口を一方向に限定せず、ぐるりと一周できるように空間をつなげる設計手法で、家の中を複数のルートで移動できる動線計画のことです。
このような回遊動線を取り入れることで、家事の効率化や家族間の動線の重なりを避けるなど、暮らしのストレスを減らす工夫が実現できます。
ここでは、そんな「回遊動線」のメリットや具体的な設計例についてご紹介します。
家事効率がアップする
例えば、キッチンと洗面脱衣室、ファミリークロークをぐるっと回れるようにつなげることで、動線が交差することなくスムーズにつながり、家事効率が格段に向上します。たとえば、洗濯機で洗う→干す→畳む→しまう、という一連の動作が最短距離で完結できるようになり、時間と手間を大幅にカットできます。
さらに、家族の誰かがキッチンにいても、もう一方から回り込めるため動線が重なりにくく、家族同士のストレスも軽減されます。
こうした工夫により、毎日の生活がより快適で効率的なものになります。

家族のストレスを減らせる
例えば、玄関からリビングへ向かう動線と、もう一つのルートとして玄関から直接パントリーやキッチンへとつながる動線を確保することで、家族の帰宅時間が異なる場合でも、それぞれがスムーズに移動できるようになります。
特に朝の忙しい時間帯や、子育て中のご家庭などでは、こうした複数のアプローチがあることで混雑や衝突を避けられ、家の中の移動が快適になります。
このような設計は、暮らしのリズムに柔軟に対応できる点でも大きなメリットがあります。

空間を広く使える
回遊動線は、家具の配置にも大きな影響を与えます。通路が複数確保されていることで、家具を壁際や部屋の角に無理なく配置できるようになり、中央の空間に余白が生まれます。この“余白”こそが、部屋に圧迫感を与えず、開放的な印象をつくり出す大きなポイントです。
また、視線がスムーズに通ることで、実際の面積以上に広く感じられる効果も期待できます。

天井高・視線の抜けで“広がり感”を演出
実際の広さを物理的に広げることは難しくても、視覚的に“広く見せる”工夫は数多く存在します。
ここでは、空間をより開放的に感じられるようにするための視覚的な演出の工夫についてご紹介します。
天井高を変えるだけで印象が変わる
天井を高く取ることで、空間に縦方向の広がりが生まれ、実際の面積以上にゆとりを感じられるようになります。特にリビングの一部に勾配天井を取り入れると、天井が視線を上へと導き、視覚的な圧迫感が軽減されます。
勾配の角度や天井の仕上げ材によっても印象は変わり、ナチュラルな木目を見せることで温かみのある開放的な空間に演出することもできます。
また、天井が高くなることで採光や通風の効果も高まり、より快適な室内環境を実現できます。

吹き抜けやハイサイドライトも効果的
2階建て住宅であれば、吹き抜けを設けることで視線が上方へと抜け、天井の高さと空間の奥行きを感じやすくなり、実際の面積以上の開放感が生まれます。特にリビングなどの共有スペースに吹き抜けを取り入れると、家族が集まる場所がよりのびやかで心地よい空間になります。
また、高い位置に窓(ハイサイドライト)を設けることで、直射日光を避けながらも柔らかく自然光を取り込み、視線が屋外へと抜けるため、より広がりを感じられます。
日中は照明に頼らずに明るさを確保でき、節電効果にもつながるのも嬉しいポイントです。

視線の抜けを意識した間取り
玄関からリビング、さらにリビングからウッドデッキへと、視線がスムーズに抜けていくような間取りにすることで、室内空間がより広く感じられます。
例えば、リビングの窓を大きく開口し、屋外と視覚的につながるようにすることで、実際には屋内だけであっても、視覚的には“奥行き”と“抜け感”が演出されます。また、玄関からの視線が廊下や壁で遮られず、まっすぐリビングの明るい窓まで届くように工夫すると、家に入った瞬間から開放感を感じられるようになります。
こうした視線の抜けを意識した設計は、限られた面積の中でも“つながり”と“広がり”を感じられる空間づくりに非常に効果的です。

パントリーや土間収納の工夫
収納を充実させることで、室内に「モノがあふれる」状態を防ぎ、見た目にもスッキリとした空間を保つことができます。とくにコンパクトな家では、限られたスペースを有効に活用するためにも、収納の配置や種類を計画的に考えることがとても大切です。
ここでは、暮らしやすさを左右する収納の工夫についてご紹介します。
パントリーでキッチンまわりをすっきり
キッチン背面にパントリーを設けることで、調味料や缶詰、米袋といった食品ストックはもちろん、使用頻度の低い調理家電や大きな鍋、買い置きのキッチンペーパー類まで一括して収納することができます。
これにより、キッチンカウンターや棚の上に物が出しっぱなしになることがなくなり、常にスッキリとした見た目を保つことが可能です。
さらに、パントリーに扉を設けておけば、急な来客があっても中を隠せるため、生活感を感じさせない美しい空間を維持できます。

土間収納で玄関を広々と
玄関に隣接して土間収納を設けることで、ベビーカーやアウトドア用品、長靴、雨具、季節物の靴類など、屋外で使うアイテムを一括して収納することができます。これにより、玄関まわりに物が散らかることなく、すっきりとした印象を保てます。
土間収納は、床をフラットにせずタイルなどで仕上げることで泥汚れや濡れたままの荷物にも対応でき、日常的な使い勝手が大幅に向上します。
さらに、玄関ホール自体を広く確保できない場合でも、土間収納があることで奥行きや抜け感を感じられるようになり、玄関全体がゆったりとした印象になります。

収納は「見せない」「まとめる」がカギ
収納スペースを複数の場所に小分けにするよりも、たとえば「日用品」「衣類」「食品」といった用途別にまとめて集約した収納を計画することで、必要なものをすぐに取り出せる利便性が向上します。
また、動線に沿った場所に配置することで、モノの移動も少なくなり、家事効率も高まります。視覚的にも収納が一箇所にまとまっていることで生活感が出にくくなり、室内がすっきりと整った印象になります。
このように“まとめる収納”は、空間を広く見せるための大切なポイントのひとつです。
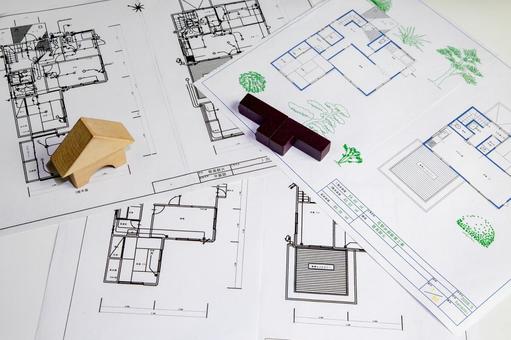
まとめ
「動線」「視線」「収納」を工夫することで、驚くほど快適で広々とした空間をつくることができます。限られたスペースをどう活かすか。それが、住まいづくりの楽しさでもあり、腕の見せどころでもあります。
ぜひ、今回ご紹介したポイントを参考に、“コンパクトでも広く感じる家”づくりを目指してみてください。

レンガの家専門 SEISYO三重支店
SEISYO三重支店ではレンガの家、クラシック住宅を中心に家づくりをしています。新築をご計画の際には、ぜひご相談ください。
お問い合わせはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://seisyo-co.jp/contact/
LINE公式アカウント
SEISYOの公式LINEアカウントでは、家づくりに役立つ知識やイベント情報をいち早くお伝えしております。これから家づくりをお考えの方は、ぜひご登録ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://lin.ee/ehujE0m
著者プロフィール
中島 盛夫
株式会社盛匠代表取締役[保有資格:二級建築士、宅地建物取引士]
大工としてひたむきに走り続けていた26歳のある日、お客様の娘様から頂いた現場での一言、 「良い家を作ってくれてありがとう」その言葉に建築への想いが膨らんでいく気持ちに気づいた私は、 「家づくりの最初から最後まで、じっくりをお客様と対話して、一生のお付き合いがしたい」と感じ、SEISYOを立ち上げました。