住宅ローンを選ぶときに、多くの方が迷うのが「変動金利」と「固定金利」のどちらを選ぶべきかという点です。
これまで長く低金利が続いてきましたが、2025年に入り、日銀の政策変更や物価上昇の影響によって、金利に少しずつ動きが見られるようになりました。ニュースなどで「金利が上がる」と聞くと不安になる一方で、「固定にしたほうがいいのかな?」「でも固定は高いし…」と悩む方も多いのではないでしょうか。
住宅ローンの選択は、家づくりと同じくらい大切な判断です。
なぜなら、同じ借入額でも金利タイプによって支払い総額が大きく変わるからです。
この記事では、2025年の金利動向を踏まえながら、「変動金利」と「固定金利」の違いや特徴、向いている人のタイプをわかりやすく解説します。
2025年の住宅ローン金利はどう変わった?
2025年は、これまでの“超低金利時代”が少しずつ終わりを告げようとしています。
日銀が2024年春にマイナス金利政策を解除した影響で、長期金利が上昇し、金融機関の住宅ローン金利にも変化が出てきました。特に固定金利型のローンでは、前年より0.2〜0.3%ほど上がった銀行もあります。
一方で、変動金利は依然として0.4〜0.7%台にとどまり、低金利が続いています。
とはいえ、金利が上がったといっても、まだ返済負担が急増するほどではありません。
問題は、これから数年先にどうなるかです。
金利上昇のスピードや幅は、経済成長率や物価、日銀の政策次第で変わるため、確実な予測はできません。ただ、金融機関各社は慎重な姿勢を見せており、2025年後半にかけても「緩やかな上昇傾向」が続くとみられています。
つまり、今の時期は「変動と固定の差が縮まり始めた転換期」といえるでしょう。だからこそ、それぞれの特徴を理解したうえで、自分に合った金利タイプを選ぶことが大切です。

変動金利の特徴と注意点
金利の動きが少しずつ変化している今、最も注目されているのが「変動金利」です。
これまでの低金利時代を支えてきた代表的なローンタイプであり、多くのご家庭が選んできた理由があります。
ここでは、その仕組みやメリット・デメリットを具体的に見ていきましょう。
変動金利の仕組みと金利の決まり方
変動金利とは、景気や市場金利の動きに合わせて、返済中に金利が変わるタイプのローンです。多くの銀行では半年ごとに金利を見直し、5年ごとに返済額を調整する仕組みになっています。
たとえば、借入時の金利が0.45%でも、将来金利が上がれば返済額も増える可能性があります。
金利の基準となるのは「短期プライムレート」と呼ばれるもので、これは銀行が企業に短期で貸す際の最優遇金利をもとに決まります。
日銀が政策金利を引き上げれば、短期プライムレートも上昇し、変動金利もそれに連動して上がるという仕組みです。

メリット:初期返済が軽く、資金計画にゆとりが持てる
変動金利の最大の魅力は、金利が低いため毎月の返済額を抑えられることです。
固定金利よりも0.5〜1%程度低くなることが多く、総返済額も少なくなります。
そのため、家計に余裕を持たせたいご家庭や、今後収入が増える見込みのある共働き世帯には人気があります。さらに、繰上返済を積極的に行えば、金利が上がる前に元金を減らせるため、返済総額をより抑えられます。

デメリット:将来の金利上昇による返済増リスク
一方で、変動金利の最大の注意点は「金利上昇リスク」です。
たとえば、金利が1%上がるだけでも、35年返済では総返済額が数百万円増える場合があります。また、金利が急に上昇しても、返済額は5年間据え置かれるため、未払い利息が発生し「元本が減りにくくなる」こともあります。
今は低金利でも、将来の経済状況によっては支払いが重くなるリスクを理解しておく必要があります。
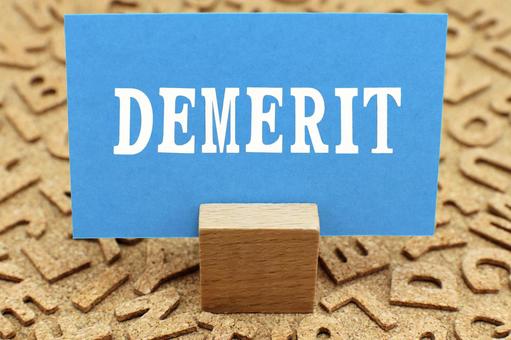
固定金利の特徴とメリット・デメリット
変動金利に比べて、安定した返済を希望する方に選ばれるのが固定金利です。
金利の動きに左右されず、返済額が変わらない安心感から、子育て中や将来の出費を見通したいご家庭にも支持されています。
ここからは、固定金利の仕組みやメリット・デメリットを順に見ていきましょう。
固定金利の仕組み(全期間固定・当初固定の違い)
固定金利には大きく分けて「全期間固定型」と「当初固定型」があります。
全期間固定は、返済期間中ずっと同じ金利が適用されるタイプで、代表的な商品は「フラット35」です。一方、当初固定型は、最初の10年や15年など一定期間だけ金利が固定され、その後は変動金利に切り替わるタイプです。
どちらも返済額が一定期間変わらないため、家計管理がしやすいのが特徴です。

メリット:返済額が変わらず、家計の見通しが立てやすい
固定金利の最大のメリットは、金利変動に左右されず、返済額が変わらない安心感です。
たとえ今後金利が上昇しても、借入時に決めた金利のまま返済を続けられるため、将来の家計計画を立てやすいのが特徴です。特に、子育てや教育費など出費の多い時期を見据えたいご家庭や、長期的に安定した支払いを希望する方に向いています。

デメリット:当初の金利が高く、借入直後の負担が大きい
その一方で、固定金利は変動に比べて金利が高く設定されています。
たとえば、同じ3,000万円を借りても、金利が1%違うだけで月々の返済は1万円以上変わることもあります。また、将来金利が下がっても返済額は変わらないため、結果的に「高い金利を払い続ける」ケースもあります。
短期間で売却や借り換えを検討している方には、固定金利はやや不向きといえるでしょう。
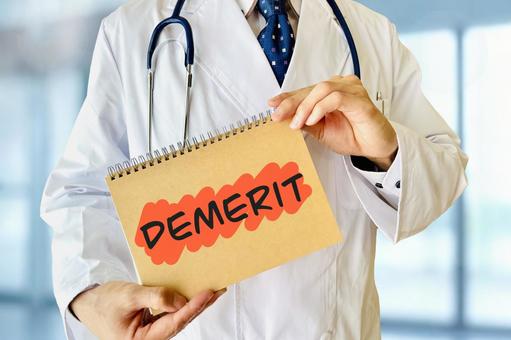
どちらが自分に合う?タイプ別に考える住宅ローン選び
住宅ローンに「絶対の正解」はありません。大切なのは、自分たちのライフプランや家計状況に合った金利タイプを選ぶことです。
たとえば、収入が安定していて長期的な安心を重視する方は、固定金利が向いています。金利上昇の心配がなく、将来の教育費や老後資金の見通しを立てやすくなるからです。
一方で、今後収入アップが見込める共働き世帯や、早めに繰上返済を予定しているご家庭は、変動金利を選ぶことで支払いを軽くしながら効率よく返済を進めることができます。
もしどちらか決めきれない場合は、「当初10年固定+その後変動型」といったミックスローンを検討するのも一つの方法です。これなら、最初の10年間は安心を確保し、その後の状況に合わせて調整する柔軟な選択が可能です。

家づくりとセットで考えるローンの選び方
住宅ローンは「借りること」よりも「返し続けること」が大切です。
金利タイプを選ぶ際は、単に金利の安さだけでなく、返済の続けやすさや家計への影響を考えることが重要です。
家づくりを検討する段階から、建築費用・外構費・諸経費を含めた総予算を把握し、「月々いくらなら安心して返せるか」を明確にしておきましょう。また、金利が上昇しても慌てないためには、ボーナス返済に頼りすぎず、繰上返済用の貯金を少しずつ積み立てておくこともおすすめです。
さらに、家を建てた後も定期的にローン内容を見直すことが大切です。借り換えや金利タイプの変更が選択肢に入ることで、将来的な家計負担を軽減できる可能性があります。

まとめ:金利よりも“安心して返せる仕組み”を選ぶ
変動金利と固定金利、どちらにもメリットとリスクがあります。今後の金利動向を正確に予測することは難しいため、「どちらが得か」ではなく、「どちらなら安心して返していけるか」を基準に考えることが大切です。
ご家庭のライフプラン、収入の安定性、将来の支出を踏まえ、無理のない返済計画を立てることが、長く快適に暮らすための第一歩になります。金利に振り回されず、安心して住み続けられる家づくりを目指しましょう。

レンガの家専門 SEISYO三重支店
SEISYO三重支店ではレンガの家、クラシック住宅を中心に家づくりをしています。新築をご計画の際には、ぜひご相談ください。
お問い合わせはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://seisyo-co.com/contact2/
LINE公式アカウント
SEISYOの公式LINEアカウントでは、家づくりに役立つ知識やイベント情報をいち早くお伝えしております。これから家づくりをお考えの方は、ぜひご登録ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://lin.ee/ehujE0m
著者プロフィール
中島 盛夫
株式会社盛匠代表取締役[保有資格:二級建築士、宅地建物取引士]
大工としてひたむきに走り続けていた26歳のある日、お客様の娘様から頂いた現場での一言、 「良い家を作ってくれてありがとう」その言葉に建築への想いが膨らんでいく気持ちに気づいた私は、 「家づくりの最初から最後まで、じっくりをお客様と対話して、一生のお付き合いがしたい」と感じ、SEISYOを立ち上げました。