レンガの家はその美しい外観と耐久性から今なお多くの人々から人気のあるデザインです。特にクラシックなデザインや重厚感を好む方々にとって、レンガの家は理想的なデザインとなるでしょう。歴史的にも、レンガは世界中でその強度が証明されており、日本国内でも有名な建造物に使用されています。レンガの家は見た目の美しさだけでなく、優れた断熱性や耐久性を持つため、長期的な住まいとして適している素材であると言えるでしょう。
また、レンガを使用した家は外壁だけでなく庭やインテリアとも調和させることで、さらに魅力的な住まいを作り上げることができます。外壁のデザインにこだわる方にとって、レンガの持つアンティークな質感は他の外壁材にはない独特な風合いとなります。
ただし、レンガの家には特有のメンテナンスがあることを忘れてはいけません。特に、日本の気候に適したメンテナンス方法を知る必要があり、それを持続することで長期にわたって快適な暮らしができるでしょう。この記事では、レンガの家を建てる際に知っておくべきデザインのコツや注意点、メンテナンスについて詳しく解説し、後悔しない家づくりのヒントをお伝えします。
さらに、レンガの家は外構やインテリアともコーディネートがしやすく、統一感のあるスタイリッシュな空間を作り出せるのも大きな魅力です。外壁デザインだけでなく、内部のインテリアにもレンガのテイストを取り入れることで、統一感のある空間を演出できます。レンガの家の美しさやその耐久性、メンテナンスに焦点を当てながら、クラシックで高品質な住宅スタイルを目指す方々へ向けて、レンガの家づくりのポイントを紹介していきます。ぜひご一読いただき、理想の家づくりの参考にしてください。
レンガの外壁の基本的な特徴

レンガを外壁材として使用する住宅は一般的にはあまり多い方ではありません。どちらかと言いますと観光地や歴史的建築物で見かけることの方が多いのではないでしょうか。しかし、レンガを新築の外壁に採用することで、他にはないオリジナリティと高級感を持つ住宅になります。レンガの独特な質感や風合いが独自の魅力が加わることとなり、年月を重ねるごとにその風合いがより深まっていきます。時間が経つごとに味わいが増し、長い期間にわたって美しい外観を維持できるのが、レンガの大きな魅力です。
レンガの素材は粘土や砂を焼き固めて製造する自然素材になります。赤茶色のレンガが最も一般的ですが、白やグレー、オレンジ系など、さまざまな色味があり、好みに合わせて選ぶことができます。
レンガの家とは?

レンガの家とは、外壁にレンガを採用して建築する住宅のことです。レンガは古くから世界中で使用されてきた建材であり、その魅力は見た目の美しさと耐久性にあります。レンガはサイディングなどの外壁材と比べ、100年以上の耐久性とメンテナンスも最小限で済むという特徴があります。
しかし、レンガの家は地震に弱いというイメージがあるかもしれませんが、現在の新築においては耐震性がとても強化されており、レンガの家でも安心して住むことができるマイホームとなります。
レンガはなぜ経年劣化しにくいのか?(耐久性のメカニズムを解説)
レンガの家は、長期間にわたって美しい外観を保ち続けることができる建築スタイルの一つです。多くの外壁材は年月とともに劣化し、塗装の剥がれや色あせが発生しますが、レンガはそれらの影響をほとんど受けません。その理由は、レンガ特有の素材の特性や製造方法にあります。レンガがなぜ経年劣化しにくいのか、その耐久性のメカニズムについて詳しく解説します。

焼成による強固な構造が劣化を防ぐ
レンガは、粘土を高温で焼成することで作られる建材です。一般的に1,000℃以上の高温で焼かれるため、内部の水分や不純物が完全に除去され、非常に強固な構造を持つようになります。
この焼成プロセスによって、レンガは以下のような特性を獲得します。
・硬度が高く、摩耗しにくい:表面が硬くなり、衝撃や摩擦に強い。
・吸水率が低下する:水を吸い込みにくいため、ひび割れや凍害を防ぐ。
・腐食しにくい:有機物を含まないため、腐敗や虫害の影響を受けない。
このような特徴により、レンガは長期間にわたって変形や劣化が起こりにくく、外壁材としての寿命を大幅に延ばすことができます。
紫外線や雨風による劣化が少ない理由
一般的な外壁材であるサイディングや塗装仕上げの壁は、紫外線や雨風の影響を受けやすく、時間が経つにつれて色あせや塗膜の剥がれが発生します。しかし、レンガはこれらの影響をほとんど受けません。
その理由は、レンガの素材自体に色が焼き込まれているため、表面の色が紫外線によって退色しにくいからです。また、レンガは無機質な素材であり、化学変化による劣化が起こりにくいという特性を持っています。
さらに、レンガは高い耐水性を持っているため、雨水が表面に浸透しにくく、長期間にわたって安定した状態を維持できます。特に日本のような梅雨があり、年間降水量が多い地域では、レンガの耐水性が大きなメリットとなります。
通気性と吸湿性のバランスがカビや劣化を防ぐ
レンガのもう一つの大きな特徴は、適度な通気性と吸湿性を持っている点です。多くの外壁材は湿気を閉じ込めやすく、結露やカビの発生を引き起こしやすいですが、レンガは微細な空隙を持っているため、湿気を吸収・放出する機能を持ちます。
この特性により、以下のようなメリットがあります。
・結露を防ぐ:湿気を適度に調整するため、内部の結露が発生しにくい。
・カビの発生を抑制:水分がこもらないため、カビやコケの発生リスクが低い。
・冬場の凍害を軽減:レンガが水を吸収しても適度に排出するため、内部での凍結膨張が起こりにくい。
特に日本の高湿度環境においては、こうした通気性と吸湿性のバランスが、家の寿命を延ばす上で重要なポイントとなります。
レンガが経年劣化しにくい理由
レンガが経年劣化しにくい理由として、以下の3つの特性が挙げられます。
①焼成による強固な構造:高温焼成によって強度が高まり、摩耗や腐食が起こりにくい。
②紫外線や雨風に強い:色あせや水の侵入による劣化が少ない。
③通気性と吸湿性のバランス:湿気を適度に調整し、結露やカビの発生を防ぐ。
これらの特性により、レンガの家は長期間にわたって美しい外観を維持し、メンテナンスコストを抑えながら快適に住み続けることができます。特に、長く住み続けることを考えた住宅選びをする際には、レンガの持つ耐久性が大きな魅力となるでしょう。
クラシック住宅の象徴、レンガの家の魅力

レンガの家は、クラシックな風合いと重厚感を持ち、特に海外の建築スタイルを取り入れたい方々にとても人気のデザインです。高い耐久性と優れた断熱性能、保温性能を誇るレンガは、歴史的にも多くの建築物に採用されてきました。日本国内でも、横浜赤レンガ倉庫や富岡製糸場などで採用され、その堅牢さが証明されています。中国の万里の長城に使われていることからも、レンガの持つ耐久力の高さは世界的に知られています。クラシック住宅としてのレンガ造りは、現代の日本においても人気が再燃しており、主に以下の3つの手法で建築されています。
①積みレンガの家
②スライスレンガの家
③レンガ風サイディングの家
それでは一つずつ解説します。
①積みレンガの家
積みレンガの家は、伝統的な建築手法であり、その風合いと耐久性で高く評価されています。この手法では、レンガを積み上げて壁を作り、その中に鉄骨を通すことで耐震性を強化しています。日本のような地震の多い地域では、特にこの耐震性能が重要視され、現代でも多くの積みレンガの建物に採用されています。積みレンガの家は、重厚感と美しさを兼ね備えた外観が特徴であり、デザイン的にも人気があります。また、断熱性や保温性にも優れており、快適な居住空間を提供します。このような特性から、積みレンガの家は長く住み続けられる理想的な住まいとして、多くの方々に支持されています。
②スライスレンガの家
スライスレンガの家は、レンガをスライスして外壁材として使用する工法で、施工が比較的簡単でコストも抑えやすいのが特徴です。通常の積みレンガに比べて、施工時間が短く、費用も抑えられるため、経済的にレンガの魅力を取り入れたい方には魅力的な選択肢となります。レンガ特有の高級感や重厚感はそのままに、建設費を削減できるため、積みレンガに比べて採用しやすい工法です。また、リフォームや外壁の張り替えにも適しており、幅広い用途に対応可能です。レンガは他の外壁材と比べコストが高くなってしまうことが特徴であるため、積みレンガに比べ採用しやすい工法と言えるでしょう。
③レンガ風サイディングの家
レンガ風サイディングの家は、レンガの外観を再現しながら、施工の手間やコストを大幅に削減できる工法です。レンガ風にデザインされたサイディング材を使用することで、クラシックで重厚感のある見た目を維持しつつ、実際のレンガの施工に比べて、材料費や工事費が抑えられます。ただし、本物のレンガに比べ、耐久性や耐火性がやや劣るという点がデメリットです。
レンガを外壁に採用したメリット

レンガを外壁に採用することは、家づくりを検討している方にとって非常に魅力的な選択肢の一つです。特に、レンガはその独特な質感や風合いから、他の外壁材にはない重厚感や高級感を持つデザイン性があります。さらに、伝統的な建築素材として長い歴史を持ち、その耐久性やメンテナンスのしやすさから、現代でも多くの住宅に採用されています。外観の美しさを長期間維持できるだけでなく、レンガは機能的にも優れた点が多くあります。これからレンガを採用するメリットについて詳しく解説していきますが、見た目の美しさ以上に、長い目で見た場合の耐久性や安全性の面でも大きなメリットが期待できますので是非、参考にしてください。
それでは、レンガを外壁に採用した際のメリットを見ていきましょう。
耐久性と長寿命
優れた耐久性と長寿命を持つレンガの外壁は、紫外線や雨風などの自然環境に非常に強く、サイディングなどの外壁材と比べると、経年劣化が起きにくい点が大きな特徴です。特にレンガの外壁は塗装が不要であるため、建物の完成後に発生する定期的な塗装メンテナンスを省ける点が大きなメリットです。これにより、メンテナンスコストを抑え、数十年にわたって美しい外観を維持することができます。さらに、レンガはその素材自体が頑丈であるため、割れや剥がれが生じにくく風雨による影響にも耐性があります。一般的な建物に採用される外壁は、時間が経つにつれて色あせやひび割れが発生することがあり、そのために先ほどお伝えしました防水塗装を施す必要があります。しかし、レンガの場合は自然素材であるため色合いが変わらず外観の美しさを保つことができます。
また、レンガは火災に対しても非常に高い耐久性を誇ります。これは、レンガが不燃材料であるため、火災が発生しても燃え広がることがなく、建物全体の安全性を確保できるからです。この耐火性能も、レンガの外壁が選ばれる理由の一つです。
遮音性・断熱性が高い
レンガの外壁は遮音性と断熱性に優れているため、外部の騒音を効果的に遮断し、静かな住環境となります。これは、特に交通量の多い場所や騒音が気になるエリアで暮らす方にとっては大きなメリットとなります。また、レンガは蓄熱性も高いため、季節に応じた快適な室内環境を維持することへの影響を持ちます。その特徴は、夏は涼しく冬は暖かく保つことができ、冷暖房費の節約にも貢献してくれるため、長期的な省エネルギー効果が期待できます。
さらに、レンガは温度変化に強く、外部からの気温変化を室内に伝えにくいという特性があります。このため、冬は外の冷たい空気が室内に入りにくく、暖房効率が高まります。一方、夏場には外気の熱が伝わりにくいため、冷房の効率も向上し、快適な住空間を作り出すことができます。
レンガ独特の風合いとデザイン性
自然素材ならではのレンガの質感は、他の人工素材では再現できないオリジナリティを持っており、時間の経過とともに深まる味わいを楽しむことができます。レンガはそれぞれ微妙な色や形の違いがあり、一つ一つが個性を持っているため、同じ種類のレンガを採用したとしても一つとして世界に同じ建物はありません。そして年月を経ることで、さらに趣が増し、クラシックで重厚感のある外観となります。
また、レンガはさまざまなスタイルの家にも採用することができる素材です。シンプルでモダンなデザインから、ヴィンテージ風のレトロな家まで、幅広いスタイルに対応できるため、オリジナリティあふれる家づくりを実現したい方にもお勧めできる素材になります。特に自然と調和するデザインを目指す場合、レンガの経年変化を楽しみながら、自然な風合いを保つことができるため、長く愛される外壁材として選ばれています。
レンガ外壁のデメリット
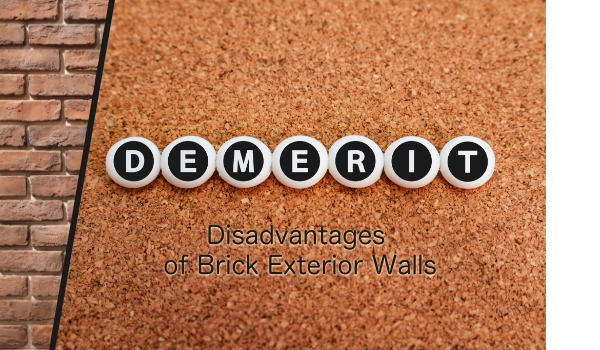
レンガの外壁には多くのメリットがある一方で、当然ながらデメリットも存在します。レンガ独特の風合いや耐久性が魅力的である反面、注意しなければならないポイントもいくつかあります。外壁材の選択肢として考える際、メリットだけではなくデメリットもしっかり把握しておくことが重要ですので、ここからはレンガを外壁に採用する際に知っておくべきデメリットについて詳しく見ていきましょう。
高額な施工費用と長い工期
レンガ外壁の最大のデメリットは、他の外壁材に比べて施工費用が高くなるという点です。特にブロックレンガを積み上げる「レンガ積み工法」を採用した場合、手作業での施工が必要なため、工期が長くなり人件費も高くなります。また、施工費用だけではなく材料費も高額になります。そのため、「レンガ積み工法」ではなく、軽量化したスライスレンガを使用した工法をお勧めいたします。
耐震性の課題
レンガは重たい素材であり耐震性が低いため、地震の多い日本ではレンガ積み工法を採用することはあまりお勧めできません。そのため建築費用と同様、軽量化したスライスレンガを使用した工法をお勧めします。スライスレンガ工法であれば、レンガを使用したとしても耐震性に優れた建物を建築することが十分可能となります。
レンガのメンテナンス方法
レンガを外壁に採用した場合、サイディングなど一般的な外壁材よりもメンテナンスが少なく済みますが、30年に一度程度、定期的なメンテナンスは必要であることを覚えておいてください。
ピンニング工法による補修
レンガタイルが浮いてしまった場合には、ピンニング工法で補修を行います。レンガタイルを固定し、浮きを改善させることで、外観を美しく保ち続けることが可能です。
レンガタイルの交換
剥がれたレンガタイルは交換する必要がありますが、交換した部分が目立つことがあります。この場合、色味を調整するためのバーナー処理などを行い、全体の風合いを馴染むように施工いたします。
レンガの外壁を取り入れる際のポイント
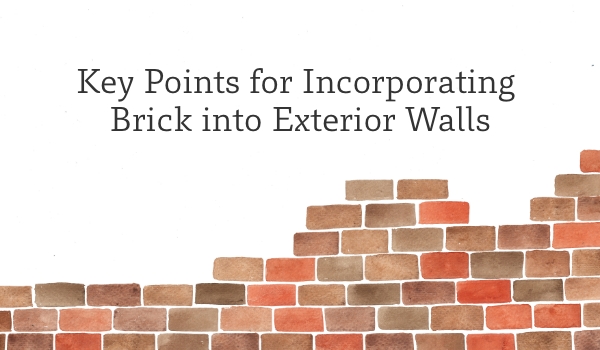
レンガの外壁は、独特の美しさと機能性を兼ね備えた外壁材です。しかし、施工費用や工期により他の外壁材に比べて高額になるため、予算や工期を考慮して選択する必要があるでしょう。また、30年に一度程度の定期メンテナンスが必要になります。レンガの家を採用する際には、経験豊富な住宅会社と共に家づくりを計画していくことをお勧めします。
日本の家と海外のデザイン住宅の違い

家のデザインは国によって多種多様であり、気候、文化、ライフスタイルの違いが反映されています。「日本の家と海外の家はどこが違うのか?」と疑問を持つ方や、「海外のようなおしゃれな家を参考にしたい」と考える方も多いでしょう。
日本と海外の住宅デザインを比較し、それぞれの特徴やメリット、どのようにして理想の家をデザインするかについて詳しく解説します。さらに、日本で海外風の家を建てる際に気をつけるべきポイントについても触れていきます。
住宅寿命と資産価値の違い

それでは日本の家と海外の家について住宅寿命と資産価値という視点で見ていきましょう。
日本の家の寿命と考え方
日本では、家の寿命は約30年と言われてきました。この背景には、戦後の急速な住宅建設が関係しており、耐久性よりもコストを優先した建物を多く建ててきたことが挙げられます。日本の家は一般的に「消耗品」として扱われ、定期的に建て替えが必要とされることが多く、資産価値は徐々に低下していきます。
しかし最近では「長期優良住宅」の考え方が広がり、耐久性やメンテナンスが重視され、長期間にわたって資産価値を保つことを目指した建物が増えてきています。私たちSEISYOの建物も「長期優良住宅」を標準仕様とし、建物の保証も最長で60年となっています。
海外の家の寿命と考え方
海外、特に欧米諸国では、家は長く住むことを前提として作られており、寿命は50年〜100年とも言われています。家は一度建てれば、世代を超えて引き継ぐことが考え方の前提であり、そのため資産として大切に扱われます。建築時には耐久性やリフォームのしやすさが重視されます。
特にヨーロッパでは、家が家族の資産として次世代に引き継がれるため、品質と耐久性を考慮して設計していきます。
間取りと生活スタイルの違い

次に間取りと生活スタイルの違いについて見ていきましょう。
日本の住宅の間取り
昔ながらの日本の住宅は、部屋ごとに区切られた間取りが主流でした。しかし、最近ではオープンな広々としたレイアウトが多く、リビングとキッチンをLDKとして一体化し、リビングに大きな窓を設けて自然光を取り入れ、家族が集まりやすい空間を作るように設計します。
また、日本の住宅には「玄関で靴を脱ぐ」という文化があります。これは、室内の清潔さを保つために重要な要素であり、玄関とリビングを明確に区別することができます。
海外の住宅の間取り
海外の家では玄関とリビングが直接つながっていることが多く、特にアメリカでは「オープンフロアプラン」が主流です。ホームパーティーなどで大人数が集まることができるようにリビングやダイニング、キッチンが一つの大きな空間にまとめられ、開放的な空間が特徴です。バスルームやトイレが複数設けられることが多く、広々としたリビングやプライベートな寝室に加え、家族全員が快適に過ごせるように設計された多くのバスルームがあります。
家全体のサイズと空間の広さ
多くの日本の住宅はコンパクトに設計されます。例えば、統計によれば日本の住宅は1戸あたりの平均床面積は94㎡(約28坪程度)とされています。対して、アメリカやヨーロッパでは、住宅の床面積は148㎡以上(44坪以上)の住宅が一般的です。特に、リビングルームやホールには吹き抜けや高い天井がより広々とした空間を演出します。また、天井の高さも海外の住宅では2.7m以上が標準ですが、日本では2.4mが一般的な天井の高さになります(メーターモジュールを採用している住宅は2.7m程度の天井の高さである場合があります)
海外のデザインの特徴

それでは海外のデザインの特徴を見ていきましょう。
カナダの住宅デザイン
カナダの住宅は、自然との調和を大切にしており、木材を多く使ったナチュラルなデザインが特徴です。厳しい冬を快適に過ごすために、断熱性や気密性が高く、温かみのある居住環境が整えられています。三角屋根や白い格子窓、大きな窓がカナダの家の代表的なデザイン要素です。
フランスの住宅デザイン
フランスでは、地域によって住宅デザインが異なります。南フランスでは、白い漆喰の壁に赤やオレンジの瓦屋根が特徴的で、地中海沿岸のリゾート感を感じさせます。一方、北フランスでは、急勾配の屋根や断熱性を考慮した小さめの窓が主流です。
イギリスの住宅デザイン
イギリスの住宅デザインは、チューダー様式が代表的で、木材とレンガを組み合わせたハーフティンバー構造が特徴です。急勾配の三角屋根や白塗りの外壁、そして露出した柱や梁が、伝統的なイギリスの家の重厚感と温かみを演出しています。
日本で海外デザインの家を建てる際の注意点

日本で海外のデザイン住宅を建てる場合、周囲の住宅や街並みとの調和について考えることも大切です。海外のデザインは日本の街並みからするととても個性的に見えます。そのため、周囲の環境を考慮したデザインを少しアレンジしても良いでしょう。また地域の気候に適した設計も重要になります。断熱性や防犯性、窓の配置や材質を地域の気候に合わせた最適な建材を選ぶことで、快適で安心して暮らすことができる住まいとなります。
文化とライフスタイルの視点から
日本と海外の家のデザインには、それぞれの国の文化や生活スタイルが色濃く反映されています。どちらにも良さがあり、それを上手に取り入れることで、理想の住まいを実現することができます。特に、海外のデザイン住宅を日本で建てる際には、周囲との調和や気候に適した設計を行いながら、個性あふれる住まいを作り上げましょう。
外観・内装コーディネートのポイント

洋風のおしゃれな雰囲気を楽しめるレンガの家が近年人気を集めています。レンガを使った家はその美しい外観だけでも魅力的ですが、外構やお庭、内装のコーディネートを工夫することによってさらにおしゃれな家にすることができます。レンガの家を建てる際に知っておきたい外観・内装コーディネートのポイントをご紹介します。
①レンガの色にこだわる
レンガにはさまざまな色があります。外壁に使用する色を変えるだけでも家の印象を大きく変化させることになるため色選びは非常に重要です。主な色として、以下の4種類があります
赤茶系レンガ:温かみとレトロ感が特徴。
素焼き系レンガ:淡い色合いで、落ち着いた雰囲気を演出。
白系レンガ:クリーンで涼しげな印象。
グレー系レンガ:モダンで洗練された印象。
これらの色を単色で使うこともできますが、複数の色を組み合わせて独自のデザインに仕上げることもできます。
②ライトアップで外観を演出
レンガの外観は、夜、ライトアップすることで一層美しくに見せることができます。レンガの表面は凹凸があるため、光の当たり具合で陰影やグラデーションを楽しむことができます。
③自然素材と組み合わせる
レンガは自然素材との相性が良いため、石や木材などと組み合わせて外観に変化をつけることができます。外壁にはレンガ、庭には石畳、さらにグリーンを取り入れることで、自然と調和した美しい景観が実現します。
④門や塀にレンガを使用する
外壁だけでなく、門や塀にもレンガを使うことで、統一感が生まれ、より美しさを演出することができます。
⑤玄関アプローチにレンガを使う
レンガを玄関アプローチに使用することで、お客様をお迎えする際に特別な演出をすることができます。全面にレンガを敷き詰めるか、部分的に使って動線を引き立てるなど、さまざまなデザインを考えてみましょう。
レンガの家をおしゃれにするポイント:内装コーディネート

レンガの家をおしゃれにする内装コーディネートのポイントについて解説します。
①ベースカラーを決める
レンガの家の内装は、ベースカラーを決めるとまとまります。たとえば、白を基調にすると明るい印象に、ブラウンを基調にすると落ち着いた雰囲気になります。家具や小物でアクセントカラーを取り入れても統一感を保てます。
②家具選びにこだわる
レンガの家には、木目を活かした家具や北欧風の家具がよく似合います。木の温かみがレンガと調和し、居心地の良い空間を作ることができます。特に、アンティーク調やヴィンテージの家具を採用することでレンガの家のクラシカルな雰囲気が引き立ちます。
③吹き抜けで開放感を演出
レンガの家に吹き抜けを取り入れることで、重厚感のある外観とは対照的に、開放感のある内装が出来上がります。
④室内にレンガを取り入れる
外観だけではなく室内の一部にレンガを取り入れることで、より個性的で統一感を持つデザインになります。たとえばリビングの一部の壁、キッチンのバックウォールにレンガを使用するとインテリア全体が引き締まってクラシック感の増したコーディネートとなります。
外観や内装コーディネートのディテールにこだわること

レンガの家をおしゃれにするためには、外観や内装コーディネートのディテールにこだわることが大切です。色の選び方、素材の組み合わせ、照明の使い方などを工夫することで個性的で魅力的な家になります。ぜひこの記事を参考に、理想のおしゃれなレンガの家をコーディネートしてください。
豪華で上品なクラシックデザインを実現するためのコーディネート方法

クラシックデザインとは、華やかさと落ち着きを兼ね備えた、贅沢な空間を演出するスタイルであり、時代を超えて多くの人々に愛され続けているデザインです。新築のコーディネートだけではなく、配置する家具にも高品質なファブリックを使うことが多いクラシックデザインは、エレガントで重厚感のある雰囲気を生み出すことができます。そんなクラシックデザインを新築のコーディネートで実現するための具体的な方法を解説します。
クラシックデザインの魅力と特徴

クラシックデザインは、ヨーロッパの古城や宮殿を思わせるようなデザインで、家具や装飾品は繊細な装飾が施されていることが特徴です。流行に左右されることが少なく、いつの時代にも愛され、そのデザインは美しさを保ち続けています。
近代的なデザインにはモダンデザインを取り入れた直線的なラインを多用しますが、クラシックデザインには曲線的なラインが多用されます。ファブリックはベルベットやサテン、シルクなど、光沢のある上質な素材を採用し、色合いは、ダークブラウンやゴールド、深いグリーンなど、落ち着いた色調が基本となります。
クラシック住宅の歴史と進化:時代ごとの特徴を知る

クラシック住宅は、時代ごとの文化や芸術を反映したデザインが特徴で、現代でもその美しさと重厚感で多くの人々に愛されています。ここからは、クラシック住宅の歴史を時代ごとに振り返り、その特徴を詳しく解説します。
ルネサンス様式(14–16世紀)
ルネサンス様式は、古代ギリシャ・ローマの建築様式を復興させたもので、左右対称のデザインや幾何学的な美しさが特徴です。住宅では、“比例”や“調和”を重視した設計が取り入れられ、エレガントなファサードや列柱がよく見られました。内部では、高い天井や大きな窓を採用し、明るく開放感のある空間を実現しました。
バロック様式(16–18世紀)
バロック様式は、豪華な装飾と動的なデザインが特徴です。この時代の住宅には、曲線を多用した外観や装飾が施された天井画、金箔を使った豪華な仕上げが見られます。窓やドアの形状も装飾性が高く、光と影を活かした演出が随所に取り入れられました。
ロココ様式(18世紀初頭—中頃)
ロココ様式はバロック様式の発展系であり、繊細で優美なデザインが特徴です。住宅では、柔らかい曲線や淡いパステルカラーが用いられ、装飾品にも花や葉をモチーフにしたデザインが取り入れられました。室内は、シャンデリアや装飾的な家具で彩られ、特にサロン文化が発達したこの時代には、美しい社交の場としての役割も重視されました。
ヴィクトリア様式(19世紀)
ヴィクトリア様式は、19世紀のイギリスを中心に発展したスタイルで、ゴシック建築やロマネスク建築の影響を受けています。この時代の住宅は、レンガ造りや石造りが多く採用され、重厚感のある外観が特徴です。屋根の勾配が急で、尖塔や飾り瓦が用いられることが一般的でした。内部は、装飾的な壁紙や彫刻が施された木製の家具が人気で、部屋ごとにテーマが異なるのも特徴です。
アールヌーボー・アールデコ様式(19—20世紀初頭)
アールヌーボーは、自然界の曲線や植物をモチーフにしたデザインが特徴で、特にステンドグラスや装飾的な鉄細工が目を引きます。一方、アールデコは幾何学的なデザインや直線的なラインを特徴とし、洗練されたモダンな印象を与えます。住宅では、アールヌーボーが優雅さを、アールデコが力強さと現代性をもたらしました。
現代におけるクラシック住宅のアプローチ
現代では、クラシック住宅の要素を取り入れつつ、快適性や省エネ性能を追求した住宅が増えています。例えば、ルネサンス様式の調和の取れた外観とモダンな設備を組み合わせたり、ヴィクトリア様式の装飾性とオープンフロアプランを融合させたりすることで、伝統と実用性を兼ね備えた住まいが実現しています。
クラシックデザインを作る5つのポイント

クラシックデザインをコーディネートするためには、重要なポイントがあります。ここでは、クラシックデザインをコーディネートするための具体的な方法をご紹介します。
①落ち着いた色調にする
クラシックスタイルにするポイントは、落ち着いた色合いを採用することです。ダークブラウンやネイビー、グリーンなどの深みのあるカラーが、空間に重厚感と格式を表現してくれます。またアクセントカラーによってより高級感を感じるデザインにすることができます。クラシックスタイル独特のエレガントさを表現するためにホワイトやクリーム色などの明るい色調を取り入れても良いでしょう。
②装飾のある家具を選ぶ
クラシックデザインでは、新築でコーディネートする壁紙や床材などだけではなく家具にも気を遣うことでより一層美しい空間を演出することができます。曲線的なデザインや、彫刻が施された木製の家具、金細工のディテールなど、装飾性の高いアイテムを選ぶと良いでしょう。このような家具はアンティークショップや専門の家具メーカーで手に入れることができます。
③高級感のあるファブリックを使用する
カーテンを選ぶ際にはファブリックの選び方が重要です。高級感と伝統を感じさせるファブリックを選ぶことで、空間全体がより一層豪華な印象になります。例えば、ベルベットやサテン、シルクなどの素材は、クラシックスタイルに合うでしょう。
④クラシカルな模様をポイントで取り入れる
クラシックデザインには、伝統的な柄を取り入れることも欠かせません。ダマスク模様やフローラルパターン、アラベスク模様などのクラシカルなデザインは、壁紙やカーテン、ラグなどに取り入れると、空間全体がエレガントで歴史を感じさせる雰囲気になります。
ただし、柄物はあまり多用しすぎず、ポイントとして取り入れることで、空間のバランスを保ちながら、クラシックな美しさを強調することができます。
⑤アンティークな照明と暖色の電球を選ぶ
最後にクラシックデザインを完成させるために重要なポイントは照明です。シャンデリアやランプなど、装飾性の高い照明器具を選ぶことで、空間全体が調和し、クラシックな雰囲気が一層引き立ちます。
また、電球には温かみのある暖色系のものを選びましょう。暖色系の照明は、空間全体にリラックスした雰囲気を与え、居心地の良い空間を作り出してくれます。
クラシックデザインを取り入れる際の注意点

クラシックデザインは、その豪華さゆえにコーディネートにはバランスが大切になります。柄物や彫刻などを多用し過ぎてしまうと空間が重たく感じてしまうことがあります。シンプルな要素と組み合わせながら統一感のあるようにコーディネートしていきましょう。
また、家具の周りにはスペースを確保できるように設計し、空間が詰まりすぎないように注意することが大切です。美しさだけではなく、快適さも忘れずに設計に取り入れていきましょう。
クラシック住宅におすすめの照明・インテリア選び

クラシック住宅では、照明やインテリアが空間全体の雰囲気を左右する重要な要素となります。ここからは、クラシック住宅にぴったりな照明とインテリアの選び方をご紹介します。
①シャンデリア
・豪華で存在感のあるデザインが特徴。リビングやダイニングに設置することで、空間全体に華やかさを与えます。
・クリスタル製や金属製のものがおすすめで、クラシック住宅のエレガントさを強調します。
②ブラケットライト
・壁面に取り付けるタイプの照明で、廊下や階段、リビングのアクセントとして最適。
・柔らかな光が壁面を照らし、温かみのある雰囲気を演出します。
③アンティーク調ランプ
・テーブルランプやスタンドランプとして使用されるアンティーク調の照明。
・木製や金属製のベースに装飾が施されたデザインが、クラシックな空間に調和します。
④暖色系の照明
・電球色の照明を選ぶことで、柔らかく落ち着いた雰囲気を作り出します。
・LED照明を使用する場合も、電球色を選ぶことでクラシックな雰囲気を損なわず、エネルギー効率を高めることができます。
インテリア選びのポイント
クラシック住宅のインテリアは時代を超えた優雅さと調和を重視します。以下のポイントを参考に、インテリアを選んでみてください。
①家具
・彫刻が施された木製家具や曲線的なデザインのアイテムを取り入れるとクラシックな雰囲気が高まります。
・アンティーク調やヴィンテージの家具を選ぶと空間全体の統一感を持たせやすくなります。
②ファブリック
・カーテンやソファの生地にはベルベットやシルク、サテンなどの高級感のある素材がおすすめ。
・落ち着いた色味やクラシカルな模様が入ったデザインを選ぶと空間がより上品になります。
③装飾品
・額縁に入れた絵画やクラシカルなデザインの時計、大理石の彫刻など、空間のアクセントとなるアイテムを取り入れましょう。
・ゴールドやブロンズの装飾品は、クラシック住宅の格式を引き立てます。
④ラグとカーペット
・ペルシャ絨毯やオリエンタルラグはクラシック住宅の床を華やかに彩ります。
・落ち着いたトーンのデザインを選ぶことで他のインテリアとの調和を保てます。
⑤壁紙とカーテン
・ダマスク柄やフローラル柄の壁紙はクラシック住宅の魅力をより引き立てます。
・カーテンは厚手の素材を選びタッセルやフリンジをアクセントにするとよりクラシックな雰囲気が際立ちます。
照明とインテリアを調和させるコツ
クラシック住宅では、照明とインテリアの調和が大切です。過度な装飾を避け、色味や質感を統一することで空間にまとまりが生まれます。また、家具の配置や照明の高さを工夫することで部屋全体がバランスよく整います。
クラシック住宅の魅力を最大限に引き出すために細部にまでこだわった照明とインテリア選びを楽しみましょう。
SEISYOが提案するレンガの家、クラシックデザイン
SEISYOでは、お客様の理想のクラシックデザインを実現するためのご提案をさせていただいております。高級感と伝統を感じさせ、空間全体のコーディネートを細部に至るアドバイスを行い、お客様のライフスタイルに合わせた上質なデザイン空間を作り上げます。
レンガの家が日本の気候に適している理由とは?

日本には四季があり、湿気の多い梅雨や高温多湿の夏、乾燥する冬など、年間を通じて気候の変化が激しい国です。そのため、住まいに求められる性能は、断熱性や湿気対策、耐久性です。レンガの家は、これらの課題を解決する優れた特徴を持っています。レンガの家がどのようにして日本の気候に適しているのかを詳しく見ていきましょう。
①湿気対策に優れた素材構造
日本の梅雨や高湿度の気候では、建材が湿気を吸収して劣化したり、カビが発生するリスクがあります。レンガは粘土を焼き固めた自然素材であり、適度な通気性を備えているため湿気を吸収して放出する特性があります。このため、レンガの外壁は結露やカビの発生を防ぎ、室内環境を快適に保つことができます。
また、レンガの経年変化によって表面にできる独特の風合いは、湿気や雨風による劣化が少なく、美しい外観を維持することができます。日本の気候特有の高湿度環境にも耐えられるレンガの性能は、快適な住まいを作り上げるための大きな利点です。
②優れた断熱性で季節を問わず快適
レンガの家は断熱性が高く、外気の影響を受けにくい構造が特徴です。夏には外からの熱を遮断し、冬には内部の暖かさを逃さないため冷暖房の効率が向上します。これは、レンガが厚みを持った素材であり熱を伝えにくい性質を持っているためです。特に、日本のように夏と冬の気温差が大きい地域ではレンガの断熱性が省エネ性能の向上にも貢献します。冷暖房費の削減だけでなく、快適な温度を自然に保つ住環境が実現します。
③高い遮音性で静かな住環境を実現
日本では住宅が密集している地域が多く、外部の騒音や生活音が気になるケースもあります。レンガは遮音性が高い素材であり、交通量の多い道路沿いや、隣家との距離が近い場所に建てる場合でも効果を発揮します。
レンガは音を吸収しやすく外部からの騒音を室内に伝えにくいため静かな暮らしを求める方にもとても最適な素材です。また、室内でのプライバシーも守られるため、家族の生活音が外に漏れることを防ぐ効果もあります。
④長寿命で経年劣化に強い
日本のように雨や台風が頻繁に発生する地域では建材の耐久性が住まいの寿命を大きく左右します。レンガは高い耐久性を誇り、紫外線や風雨による影響を受けにくいため、他の外壁材に比べて経年劣化が少ない点が魅力です。また、メンテナンスの頻度が少なく済むため長期的なコストパフォーマンスにも優れています。外壁塗装の必要がほとんどなく、数十年にわたり美しい外観を維持できるため、住宅の資産価値を高める効果も期待できます。
レンガの家が快適な住空間を提供する秘密

レンガの家はその構造的な特徴と性能によってそこに住む人は快適さを感じることができるでしょう。レンガの家が快適な住空間を作り出す理由についてさらに詳しく見ていきます。
高い防火性能で安心感を提供
レンガは不燃性の素材であり火災に対して非常に強い耐性を持っています。火事が発生しても燃え広がることがないため、家族の安全を守るとともに住宅そのものの被害を最小限に抑えることができます。
自然素材ならではの健康的な環境
レンガは化学物質を含まない自然素材であり、室内環境に悪影響を与える心配がありません。また、湿度を調整する効果があるため、室内の空気が乾燥しすぎたり湿気がこもったりすることを防ぐことができます。このような特性はアレルギーや喘息を持つ方々にとっても理想的な住環境となるでしょう。
時間とともに深まる風合い
レンガの家は時間が経つほど味わい深くなり、その独特の風合いは歴史を感じさせながらも古めかしさを感じないという特徴があります。経年劣化ではなく、むしろ経年美化と呼べる変化を楽しむことができる点がレンガの家ならではの魅力です。これは、長期間にわたって愛着を持って住み続けられる理由の一つです。
日本と海外の住宅デザインの違いを知る
家づくりを考える際に、「日本の住宅はなぜ寿命が短いのか?」「海外の住宅はなぜ資産価値が維持されるのか?」と疑問に思ったことはありませんか?日本と海外の住宅デザインには、気候や文化、建築思想の違いが大きく影響しています。この記事では、日本と海外の住宅の寿命に焦点を当て、それぞれの考え方の違いや、資産価値を高めるためのポイントについて詳しく解説します。
日本の住宅の寿命と考え方:短いライフサイクルの背景とは?
日本の住宅は一般的に平均寿命が30年程度と短く、建て替えをするという考え方が根底にあります。これは、耐震基準の変化、気候の影響、税制の仕組みなどが関係しています。さらに、新築市場の活性化や流行の変化が住宅の短命化を加速させています。
日本の住宅寿命はなぜ短いのか?
先ほどお伝えしました通り、これまで日本の住宅の平均寿命は約30年と言われてきました。これは、アメリカ(約55年)やイギリス(約77年)と比べてもかなり短い数字になります。この背景には以下の要因があります。
建て替えを前提とした家づくり
日本では、「住宅は消耗品」という考え方が根強く、木造建物の償却期間は22年とされているため、築20年を超えると建物の価値はほぼゼロになり、リフォームよりも建て替えが選ばれることが多くなります。
法制度と税制の影響
日本の固定資産税は築年数とともに減額されるため、築年数の長い住宅は税負担が軽くなる仕組みです。しかし、新築住宅は税制優遇されることが多く、そのため、新築市場が活性化しやすい環境が整っています。
気候の影響と耐震基準の変化
日本は湿気が多く、地震が頻発する国です。そのため、住宅は定期的に補修を行う必要がありますが、築年数が経過した家は新しい耐震基準を満たしていないケースが多く、リフォームよりも建て替えが選ばれることが一般的です。
トレンドの移り変わりが早い
日本では、「流行のデザインを取り入れる」という考え方が住宅にも適用される傾向があります。そのため、住宅のスタイルも数十年ごとに変化し、古いデザインの家はリフォームよりも建て替えられるケースが増えます。
海外の住宅の寿命と考え方:資産価値が続く家づくりのポイント
海外の住宅は、資産としての価値を重視し、長く住み続けられるよう設計されています。そのため、適切なメンテナンスや耐久性の高い建材の使用されています。また、欧米では家を世代ごとに引き継ぐ文化があり、長期的な視点で住宅の品質を維持する意識が根付いています。税制や金融制度もリノベーションを促進し、築年数が経過しても資産価値を保ちやすい仕組みが整っています。
海外、特に欧米諸国では、住宅の寿命は50年以上、場合によっては100年を超えることも珍しくありません。その理由を見ていきましょう。
「家は資産」という考え方が根付いている
欧米では、住宅は「長く住み続ける資産」として扱われます。そのため、家の価値を維持・向上させるために定期的なメンテナンスや部分的なリフォームが一般的に行われます。
中古住宅市場が活発
アメリカやヨーロッパでは、中古住宅の価値がしっかり評価されます。リノベーションを重ねて住み継ぐ文化があるため、新築にこだわる人が少なく、築50年以上の住宅でも高い資産価値を保つことができます。
しっかりとした構造と耐久性のある素材を使用
海外では、レンガや石材など、耐久性の高い建材を使うことが一般的です。これにより、経年劣化が少なく、長期間住み続けることが可能になります。
リフォーム・修繕文化の定着
日本ではリフォームよりも建て替えが選ばれることが多いですが、海外では家の一部を修繕しながら住み続けるのが一般的です。例えば、屋根や窓を交換しながら家全体の耐久性を維持することで、家の寿命を延ばしています。
長く住み続けられる家を実現するために
日本の住宅も、適切なメンテナンスや計画的なリフォームを行えば、50年以上住み続けることが可能です。そのためには以下のような仕様や入居後の対策を取り入れることが重要になります。
・耐久性の高い素材を選ぶ(レンガ・無垢材など)
・定期的なメンテナンスを行う(屋根・外壁の補修)
・リフォームやリノベーションを積極的に取り入れる
・資産価値を意識した家づくりを考える(長期優良住宅など)
長期的な視点で考える住宅選びの重要性
日本と海外の住宅デザインの違いは、単に見た目だけでなく、「住宅に対する考え方」に大きな違いがあります。日本では「住宅は消耗品」として捉えるケースがありますが、海外では「家は資産」としてメンテナンスしながら住み続ける文化が根付いています。もし「長く住める家を建てたい」と考えているなら、海外の住宅のように耐久性や資産価値を意識した家づくりを参考にしてみるのも良いでしょう。
この考え方を取り入れることで、日本の住宅もより長持ちし、価値を維持することが可能になります。
“本物志向”が求められる今、レンガの家が選ばれる理由
近年、住宅選びにおいて「見た目の美しさ」や「耐久性」だけでなく、素材そのものの質や背景にあるストーリーを重視する方が増えています。
特に、フェイクではない“本物の素材”を求める声が強まる中で、レンガという自然素材の価値はあらためて見直されつつあります。また、中古住宅市場が徐々に活性化していく中で、**「時間が経っても魅力が失われない外観」は、その家の資産価値を左右する大きな要素のひとつとなっています。
レンガの家は、年を重ねるごとに風合いが深まり、“古くならない”どころか“美しく育っていく家”**として、多くの方に選ばれています。
家づくりに「長く住み続ける」以上の価値を求めるなら。
これからの時代こそ、“本物”の素材に囲まれた暮らしを選んでみてはいかがでしょうか。

高まる“素材への関心”とレンガの再評価
住まいに使われる素材へのこだわりは年々強まり、環境や健康への配慮も求められるようになっています。そんな中で、自然素材であるレンガは、加工が少なく、有害物質を含まない安心の素材として再注目されています。
経年変化を“味わい”に変える住宅選び
家が古くなることをネガティブに捉えるのではなく、時間と共に風合いが深まることに価値を見出す方が増えています。レンガの家は、その「経年美化」を体感できる代表的な住宅スタイルです。
持続可能な住まいづくりとレンガの親和性
近年注目されるサステナブルな家づくりの流れにおいても、長寿命でメンテナンスが少ないレンガの家は理にかなった選択肢といえます。環境負荷を抑えつつ、長く快適に暮らせる家づくりを考えるなら、レンガは強い味方となるでしょう。

ビルトインガレージを入れたいならこの形状!設計士が選ぶ、失敗しない土地条件とは?
車社会である日本において、ビルトインガレージ付きの住宅は機能性とデザイン性を両立できる人気のスタイルです。しかし、ビルトインガレージを導入するには、どんな土地でも良いというわけではありません。土地の形状や接道条件によっては、思い描いていたプランが成立しない場合もあるのです。この記事では、ビルトインガレージを前提とした家づくりを検討している方に向けて、土地選びの際に注意すべきポイントや、適した土地の条件について詳しく解説いたします。
ビルトインガレージとは?
ビルトインガレージとは、建物の1階部分に車庫スペースを組み込んだ住宅のことです。建物と一体化しているため、雨の日でも濡れずに乗り降りできる点や、防犯面の安心感、敷地を有効活用できることなどが主なメリットです。一方で、建ぺい率や容積率に影響を及ぼし、間取りにも制約が生じる点には注意が必要です。
ビルトインガレージに不向きな土地の特徴
旗竿地(敷地延長)
車の出し入れがしづらく、車幅や通行に関するストレスを感じることになるでしょう。
接道が北側のみの土地
ガレージを北側に配置すると、リビングなど主要な居室の日当たりが悪くなるケースがあります。
間口が狭い土地
ビルトインガレージは車の幅だけでなく、人の動線や玄関スペースも必要になります。間口が極端に狭いと、設計に大きな制限がかかります。
傾斜のある土地
スロープ設計や段差処理が必要となり、コストや使い勝手の面で難しさが出てきます。
ビルトインガレージに適した土地の条件
間口が6.5m以上ある整形地
ゆとりある間口があれば、車1台分の幅と出入り動線、玄関スペースをバランス良く配置できます。
接道が南または東側にある土地
日当たりを確保しながらガレージと居室の配置バランスを整えることができます。
前面道路が幅4m以上ある
車の出入りがスムーズで、安全性も確保できます。敷地へのアプローチの自由度も高まります。
平坦な土地
ガレージ設計がしやすく、スロープなどの追加工事が不要となるため、コストを抑えられます。
第一種住居地域や第二種住居地域
建ぺい率・容積率にある程度の余裕があるため、ガレージ込みでも住空間を圧迫しにくいです。
ガレージと暮らしをつなぐ間取り計画
ビルトインガレージは単なる駐車スペースではありません。生活空間との動線や収納の連携など、暮らしの利便性を向上させる工夫が求められます。
・LDKを2階に配置して採光を確保
・ガレージから室内への動線に土間収納やシューズクロークを設ける
・ガレージ上部にルーフバルコニーをつけて有効活用する
土地選びは“建物ありき”で考える
ビルトインガレージを叶えるためには、建物のプランをある程度固めておくことが重要です。土地先行で購入してしまうと、思い描いていたガレージ付きの家が建てられないという事態にもなりかねません。建築士や住宅会社と連携し、建物と土地を一体で考えることが、理想の家づくりへの第一歩となります。
まとめ
ビルトインガレージを取り入れた家づくりには、土地選びの段階から綿密な計画が必要です。間口や道路条件、方位、敷地の形状など、さまざまな要素を確認しながら進めることで、後悔のない選択が可能となります。家づくりのご希望にビルトインガレージが含まれている場合は、ぜひ建築士や住宅会社と連携しながら、土地探しを進めてみてください。
こんな人はレンガの家を選ぶべき!3つのタイプ別診断
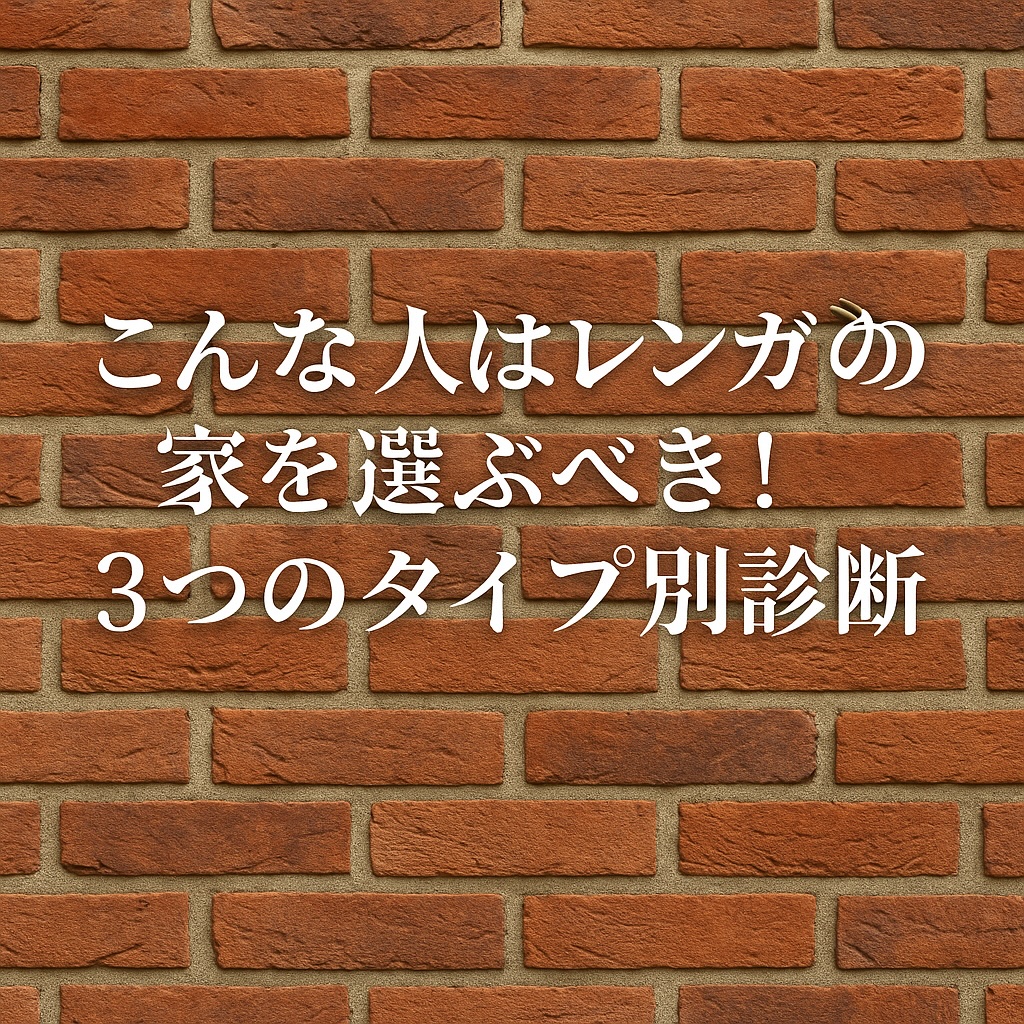
レンガの家は見た目の美しさや耐久性で人気ですが、実は「どんな人に向いているのか」を知らないと後悔することも。家は一生に一度の大きな買い物であり、選ぶ素材やデザインは人生を左右する大切な要素です。レンガの家ならではの特徴を理解した上で、自分に合った住まいを見つけることが大切です。ここでは、レンガの家を本気で考えるべき3タイプを診断形式で紹介します。あなたはどのタイプ?
とにかく「見た目重視」!おしゃれなデザインを追求したいあなたへ
おしゃれなデザインを大切にする方は、外観から室内まで細部にこだわりたいものです。周囲と差をつける独自性や、経年変化を楽しめる風合いは、レンガの家ならではの魅力です。
✅ SNS映えする外観が欲しい
✅ 人とは違う家に住みたい
✅ 経年変化の味わいを楽しみたい
診断結果:あなたは“デザイン派”! レンガの家のクラシック感と経年美化がピッタリ。レンガの独特の風合いや、ひとつひとつ微妙に違う色合いが、家全体に個性的な雰囲気を与えます。年月とともに深みを増すため、年を重ねるごとに愛着が湧き、周囲から「素敵な家だね!」と褒められること間違いなしです。
メンテナンス費用を抑えたい!手間を減らして長く住みたい堅実派
メンテナンスを重視する方は、日々の生活をより快適に、そして安心して長く暮らすことを大切にしています。例えば、外壁の塗装や補修にかかる手間や費用をできるだけ減らしたいと考える方にとって、レンガは非常に理想的な素材です。塗装不要で、メンテナンスの負担を最小限に抑えられるため、長期的に安心して暮らせます。
✅外壁の塗装は面倒
✅ 将来の維持費を考えると自然素材が安心
✅ メンテナンスコストを減らしたい
診断結果:あなたは“メンテナンス重視派”! 耐久性バツグンで塗装いらずのレンガ外壁が最適。レンガは塗装の必要がなく、手間を省けるのに加え、風雨や紫外線にも強く経年劣化が少ないため、将来的なメンテナンス費用を大幅に抑えられます。スライスレンガならコストも抑えて見た目もOK。
「家は資産」!将来的に資産価値を残したい本物志向
資産価値を重視する方は、単なる家ではなく、次世代にも誇れる財産を築きたいという思いを持っています。家族の歴史や思い出を紡ぎながら、価値の高い住まいを残すことにこだわる方には、レンガの家の魅力が響くはずです。
✅ 家は資産として残したい
✅ 安っぽい素材はNG
✅ 代々受け継げる家に憧れる
診断結果:あなたは“本物志向派”! レンガの家の耐久性・資産価値・経年美化を活かせるタイプです。レンガは、紫外線や風雨の影響を受けにくく、長期間美しさを保ち続けられる素材です。さらに、長寿命で維持費を抑えられるだけでなく、年月を経るごとに風合いが増し、独特の味わいが楽しめる魅力も。時間とともに価値を高める、資産価値の高い住まいを手に入れましょう。
レンガの家専門 SEISYO三重支店
SEISYO三重支店ではレンガの家、クラシック住宅を中心に家づくりをしています。新築をご計画の際には、ぜひご相談ください。
お問い合わせはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://seisyo-co.jp/contact/
LINE公式アカウント
SEISYOの公式LINEアカウントでは、家づくりに役立つ知識やイベント情報をいち早くお伝えしております。これから家づくりをお考えの方は、ぜひご登録ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://lin.ee/ehujE0m
著者プロフィール
中島 盛夫
株式会社盛匠代表取締役[保有資格:二級建築士、宅地建物取引士]
大工としてひたむきに走り続けていた26歳のある日、お客様の娘様から頂いた現場での一言、 「良い家を作ってくれてありがとう」その言葉に建築への想いが膨らんでいく気持ちに気づいた私は、 「家づくりの最初から最後まで、じっくりをお客様と対話して、一生のお付き合いがしたい」と感じ、SEISYOを立ち上げました。